
今回は「飲食店のファンを増やすためにYouTubeをどう活用すべきか」という題材の考察。
現在、コロナウイルスの影響により飲食業界も大きなダメージを受けている。
テイクアウトを行うお店、ネット販売に切り替えるお店、サブスクモデルを繰り出すお店、もう限界を超え閉店するお店。
様々な状況下に立っている今、ファンを増やすことに注力を注いでいる企業もある。
飲食店にとってこの状況をどう乗り越えていくか大きな課題になっている。
飲食店のファンを増やすには?
個人で飲食店、レストラン経営を行なっている事業者にとってのファンとはどういう状態を指すのか考えてみる。
僕はある種「ポジショニングの考え方」に近い部分と、スタッフの気配り、接客サービスである「人の部分」が重要だと考えます。
①ポジショニング

例えば、自分の居住区で考えると、「焼肉で美味しいと言えば〇〇。あのお店は間違いないよね」というように、
「子供に人気のあるYouTuberと言えば、HIKAKIN」
「高級なチョコレートと言えばGODIVA」
「〇〇と言えば〇〇」というポジションをとるのがポジショニング。
唯一無二の存在になるのが理想。
その根底には、そのお店が好き、人に勧めたいという欲求も満たすことができる心理。
言葉だけだと簡単に言えますが、
ファン化という状態には、様々な要素が混合していることもあると思います。
②ブランディング

ブランディングとは「ブランド」を作っていくこと。
日本でいうブランドとは、先ほどのポジショニングに近い考え方もあります。
「〇〇と言えば〇〇」というように、「ターゲット層(消費者)の頭の中にパッと出てくる存在」
かつ、それを利用することで得られる未来。それによって価値を感じる「消費者にとって唯一無二の存在」
一方で利用者、世間的が評価する「ブランド」という見方をすると
・100年以上の歴史がある老舗の料亭。
・天皇家や政治家の多くが利用する高級ホテル。
・輝かしい功績を残した選手を輩出した名門ジム。
というような施設やお店も周りにあると思います。
近年、ビジネス用語として用いられる自分でブランドを構築する「セルフブランディング」
飲食店で考えていくと、コンセプトやサービスの内容、店内の世界観(空間)の価値提供。
インスタの場合だと、タイムラインの世界観を統一しましょう。というのもセルフブランディングの1つ。
③「人」として好き

なんだかんだ言っても「人に部分」は大きいと感じてます。
単純に料理が美味しくても、接客の態度や気配りがないなど、居心地も評価されるのが飲食店。
たまに「料理は美味しいのに愛想が全くない」というお店ありませんか?
そういうのが好きな人もいますが、私はダメな派です。
いつも声をかけてくれる。
しかも建前ではなく、親近感を持って接してくれる。
料理の味はもちろんの事、利用者の期待以上に価値提供する事で「感動」に繋がり、その感動を超えていくと人はファンになります。
SNSでも同じように「尊敬型・共感型」とファン化する要素があります。
ではYouTubeを活用してファン化するためにはどのような考え方になるのか考察してみます。
ファンを増やすYouTube活用法

対面のサービスとは違い、一方的に情報発信する(視聴者は見る・聞く)という状態はSNSに近いです。
インスタでもツイッターでも、ファン化しているアカウントはあると思います。
飲食店がYouTubeでファンを増やすために大事になってくるのは
・人の部分を見せる→どんな人やお店なのか
・共感を売りにするか、尊敬される内容を見せるか
・ストーリーが見えるか。
このようなファン化する要素は共通しているはずです。
まずは認知>興味関心から>尊敬・共感>感動と信用が生まれ>ファンになる
この流れは購買行動と同じです。
ということは、「ファンになる」から逆算すると
「感動させる・信用が生まれる」ために「尊敬型か共感型」の動画を活用していくこと。
それに「興味・関心」を持ってくれるターゲット層へ「認知」してもらうこと。
すでに視聴者がいる場合であれば、尊敬型・共感型 → 感動させる、感情を動かす、人を見せる。
となると、露出を増やしてターゲット層との接触頻度をあげていくこと、コミュニケーションも必要になってきますね。
YouTubeの場合、動画にコメントする事ができます。
視聴者とのコメントのやり取りや、企画募集などを行いコミュニケーションを図ったり、ライブ配信で生のユーザーとやり取りするなどですね。
不思議と何度も何度も見てたり、動画を見る機会が増えていくにつれ、親近感は自然と湧いてくるものなんですね。
なので、YouTubeで配信する動画のジャンルの割合を設計したり、
一定期間、動画を配信してジャンルごとにどのような数値が出ているのかなども計測して改善していきます。
勘違いしてはいけないのが、「今の視聴者が求めている動画を制作する」・・という思考ではなくて、
自分たちのターゲット層(ペルソナ)の視聴者を想定して「ペルソナに響く内容を配信・動画」を作っていく思考です。
ペルソナ設定・・理想の顧客像(妄想ではなく、リアルで設定すべき)
YouTubeで発信する動画のジャンル

おそらくこのコアな部分は企画の内容、戦略に大きく関わってくるので他のサイトではなかなか公開していない、もしくはここまで設計していない(編集するだけ)と思います。
なので1つの例、フレームワークとして公開していきましょう。
②普段の様子(ライフスタイル)
③モチベーション(意識、コンセプト、人が見える)
④あえて編集しない(こだわった編集なしのありのまま)
⑤コラボ(ゲストを呼ぶ、別の企業、YouTube系)
割合は①がメイン。②〜④は業種業態、ターゲット層に合わせて調整。⑤は序盤では必要なし。
そして出口戦略です。
結局、YouTubeを見てもらってどんな行動をとってもらいたいかって部分です。
お店に行きたいのか、何かのイベントに参加したいのか、LINE@やサブスクなどへなのかなど。

その前にインスタグラムへ誘導して申し込みみたいな導線もありますが、
今回はファン化がテーマなので、やはり人の部分。
よくある例でいくと、そのお店に行ってみたいと言うよりも、出演しているスタッフなど「その人」に会いに行く、その人に相談したいなど。
心理学的な要素も含まれていますが、とにかくファン化と言うことはなんどもYouTubeを通じて、コミュニケーション、価値観の共有、人の部分に魅力を感じて信頼する。
更新しなかったら心配までしてくれるくらいファン度が高くなると、ちょっとした告知でも十分に広告効果を期待することもできますね。
いくらその会社の設備がよくても、いくらその会社の商品が魅力的に見えても、
紹介している人や、スタッフ対応が悪い、愛想の「あ」の字も無かったどうですか?
満足度120%になるわけもないでしょう。(稀にMな人もいますが・・)
出口戦略を設計しよう

企業がYouTubeを活用する際、最終的に「集客」に繋げたいという「希望・要望」がほとんどだと思います。
例えば、最終的に売上や申し込みなど利益になる場合、顧客となる人たちが何かしらのアクションが必要になってきます。
・来店してもらう(イベント、フェアなど)
・資料請求してもらう
その行動を「どのプラットホームからしてもらうか」も大事ですね。
例2:YouTube → ウェブサイトやLP → 問い合わせフォーム
例3:YouTube → LP → LINE登録 → 教育 → 販売
これも自社だけのことを考えるのではなく、ユーザーにとって一番利便性の良い部分も加味すると良いと思います。
このように、YouTubeの運用は戦略的に企画運営を行なっていくのも重要なことだと思ってます。
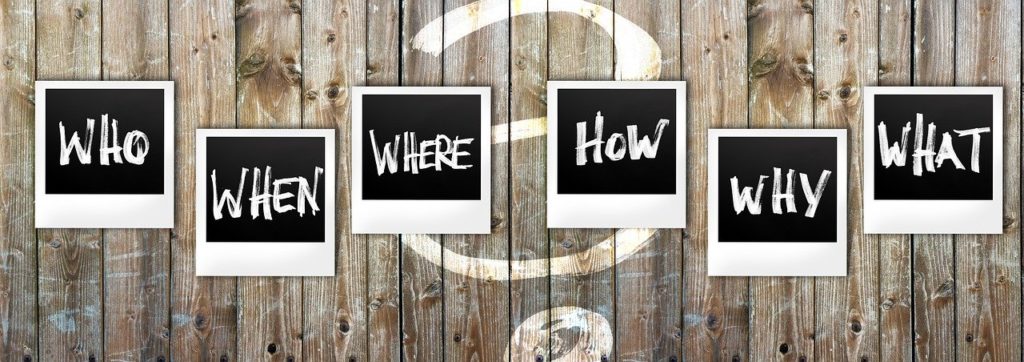
自分たちが面白いと思う動画、自分たちが配信したい企画という考えよりも、
視聴者がどんなコンテンツを企業チャンネルで発信していけばファンになるか?と言う観点から設計していくことが大事なことだと考えています。
いつもプロモーション動画だけアップしているチャンネルで、本当の意味でファンにはなりずらいですよね。
おしゃれな動画だ〜とか、しっかり作ってあるね〜と言う印象は持ってくれると思います。
ファン化と言うことで考えると、YouTubeから入ってくる人たちだけでなく、既存顧客との繋がりも見せることに利用することもできますよね。

自分が担当してくれた人がYouTubeに出て、普段のライフスタイルや、仕事への想いや風景などを見るだけで、お客さんとしては自然と親近感も湧いてきますし、思わずコメントもしたくなるものです。
定期的にコミュニケーションをYouTube(インスタでも同様)で取ることによって、継続的に「人」としての部分で繋がることになるのではないでしょうか。
まとめ
今回はファン化させるために企業がどんなYouTubeを活用していけば良いのかという話でしたがいかがでしたか?
「う〜ん。難しいかな?」
「ちょっとやってみるか!」
などなど、それぞれ会社によって人材や時間などもあるので「自社運営の方がメリットが大きい」のか「外注化して本業に専念すべき」なのかは会社の状況によって異なると思います。
もし、この記事をご覧になっている企業さん、担当者の方にとって選択肢の1つとして参考になれば幸いです。
結構、ボリュームありましたね!今回の記事は・・。
ご不明な点やわからないことなどあれば相談も当然行なっています(zoomで可能です)
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
