ブログをご覧になっていただきありがとうございます。
YouTube運用代行を行なっておりますAVENIRの山﨑です。
今回は『YouTubeで伸びてるチャンネルを丸パクリしてもうまくいかないケース』というテーマです。
実はYouTubeのノウハウで『伸びているチャンネルを模倣する』=モデリングして関連表示を狙う。
という手法で、実際に伸びるケースと伸びないケースがあるという話です。
では何が違うのか?という根本的な部分をご紹介したいと思います。
※12月末まで特別モニター企画を開催しています(詳細はこちら)
人気YouTubeチャンネルをマネして失敗するケース
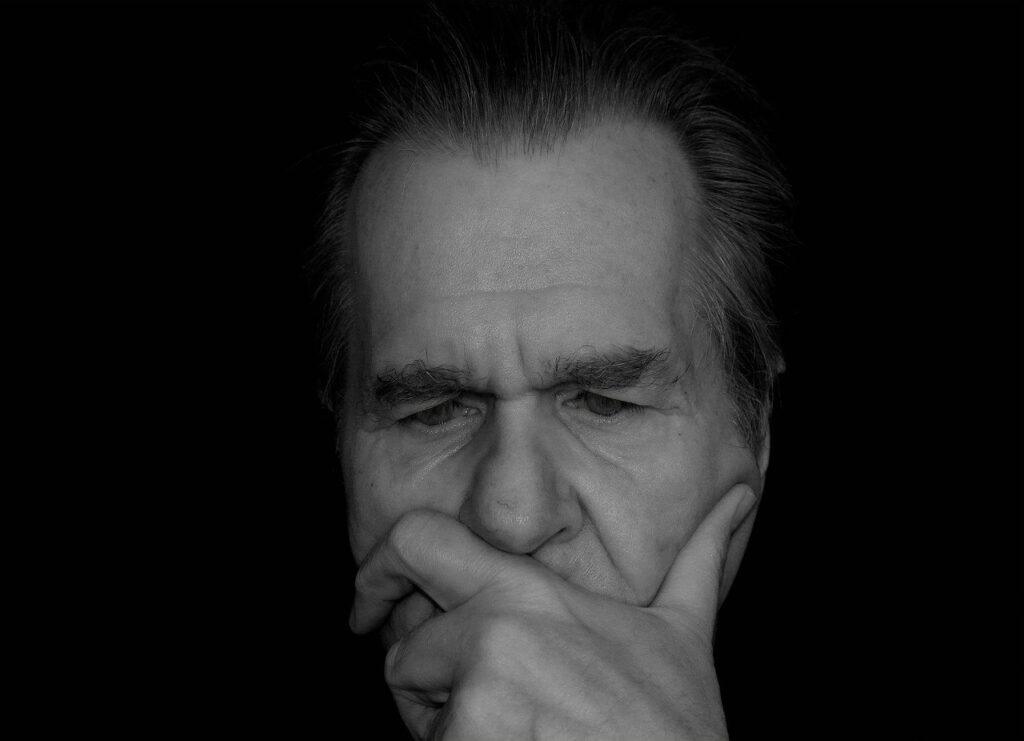
先ほども書きましたが、同業界で同じようなジャンルを発信する場合、リサーチ(競合調査)は当然重要になってきます。
まずは、そのジャンルにどのくらい視聴者が(YouTubeの市場の中で)どれくらいいるのか?
そして「どんな動画がよく見られているか」「どんなことを求めているのか」という部分はリサーチすべきです。
そして実際に「人気チャンネルをモデリングする」という手法は多くのチャンネルが実際に行なっていることです。
実は「動画の構成・オープニング・編集の仕方・テロップの種類・サムネイル・BGM」まで全部同じにしているチャンネルもあります。
でも、同じように編集や設定を行なったとしても・・・・
うまくいっていないケースはあるのです。
セミナーや有料noteなどでも配信されてるこの「モデリングの手法」ですが、
確かに効果がある部分もあるのですが、それが絶対的なノウハウではない。という話。
見た目だけ真似してもダメだということ。
では、何が重要なのかというと、まずモデリングは何のために行うのかを正しく理解するべきだと思ってます。
モデリングする本当の意図とは
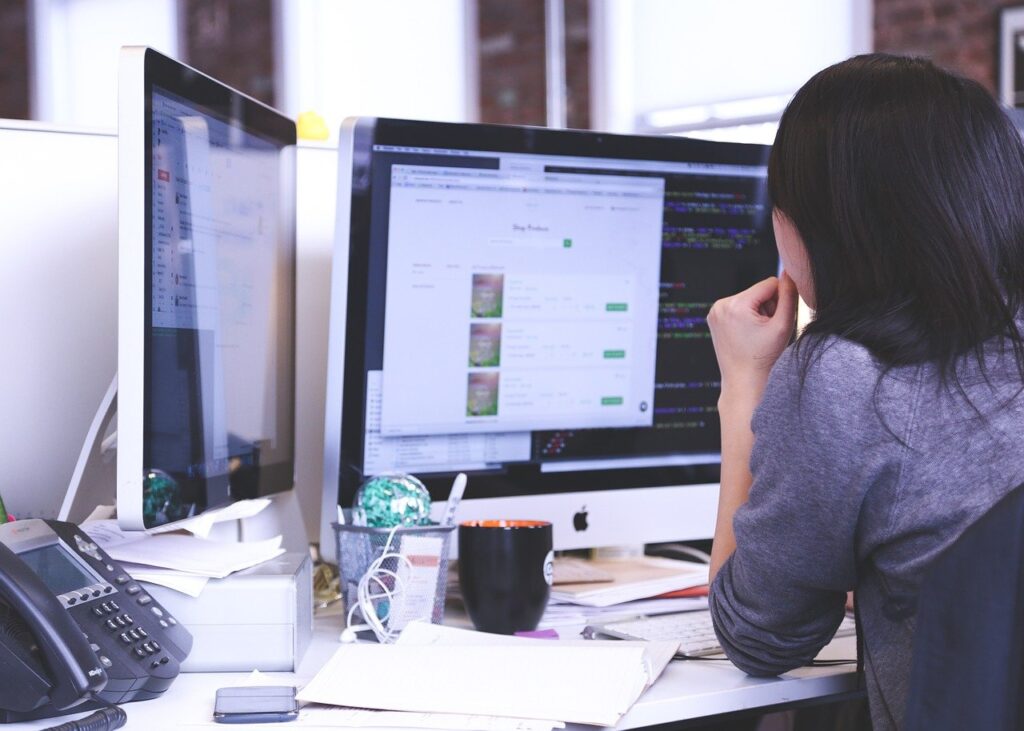
YouTubeチャンネルが伸びるタイミングというのは、チャンネル開設からいきなりバーン!!!とは伸びにくく、
一般的な数値でいくと3ヶ月〜から徐々に反応が変わってくることが多いです。
これはYouTubeのAIが『この動画(チャンネル)は、どんな動画を配信しているチャンネルなのか』を理解することから始まります。
投稿本数によって当然差は出てくるのですが、どんな人が見るチャンネルなのかをYouTube側も判断しているということですね。
つまり、モデリングするのは「見た目」だけではなくて、「どんな視聴者が」「どんなことを知りたい見たいと思って見ているのか」
伸びている動画があれば、よりその視聴者にとってもっとわかりやすく、魅力的な動画を作る1つの指針になる。
という見方が大事だと思います。
ちなみに、サムネイルやタイトルをほとんど同じにして関連動画に載せる、バズらせるという攻略法的なものは一時期ありました。
でも、長続きしない上に、視聴者は『誰を見るか』を選べます。だからこそ、見る人にとって魅力的な動画を作ることが重要だと私は思います。
YouTubeのノウハウよりも重要なこと

YouTubeのノウハウというと『どうやったら再生回数が伸びるか』『チャンネル登録者数が増えるか』という狙いから
『タイトルの付け方』や『タグの設定』『説明文の書き方』というテクニックを重視する人もいます。
これまでいろんな設定や、ノウハウなども私自身学んだり試したりしましたが、
それよりも、もっと重要なことがあると思ってます。
それは『動画の質』です。
この場合の質とは『見た目の質』というよりも、先ほど話したような『すでに伸びている動画よりも、もっと良い動画コンテンツである』という中身の濃ゆいものを作るという意味が強いです。
いろんな要素が含まれるのですが、SEO対策でも同じように、視聴者(ユーザー)が知りたいことを、よりわかりやすく解説していたり、
より役立つようなコンテンツが、結果的にGoogleで上位表示されているという事実があります。
ということは、YouTubeも同じように、見ている人にとって、同じようなジャンルやテーマだとしても、
過去に配信された動画よりも、もっと優れている内容であれば自然と数値には反映されてくるはずなんですね。
ここがYouTubeというより『動画であること』が深く関係してくるのではないかと思います。
動画は『文字よりも情報量が多い』というのはみなさんご存知だと思いますが、良くも悪くも情報量が多い。
言い方を変えると『文字だと文章だけ良いもの』だと見やすいし、内容が濃ゆければ評価されやすいと思いますが、
『動画』の場合は『人物、見た目、声、表情、話し方、雰囲気・・』いろんな要素が加わってますよね?
そうなんです。
話している内容は本当に良かったとしても、どう伝わるかは言葉(文字)だけではないんです。
見た目や声のトーンがボソボソ話していると、『何言ってんだろ?』と離脱しますよね。
どれだけすごい経歴があったとしても『感じが悪い』動画であればどうですか?また見ようとは思わないですよね。
つまり、情報量が多い分、見た目や内容・話し方など、全体的な質を上げることも大事になってくると思います。
ここを理解せずに見た目だけをパクっても二番煎じになってしまい、結局YouTubeからもオススメはされないです。
YouTubeの丸パクリでうまくいく事例
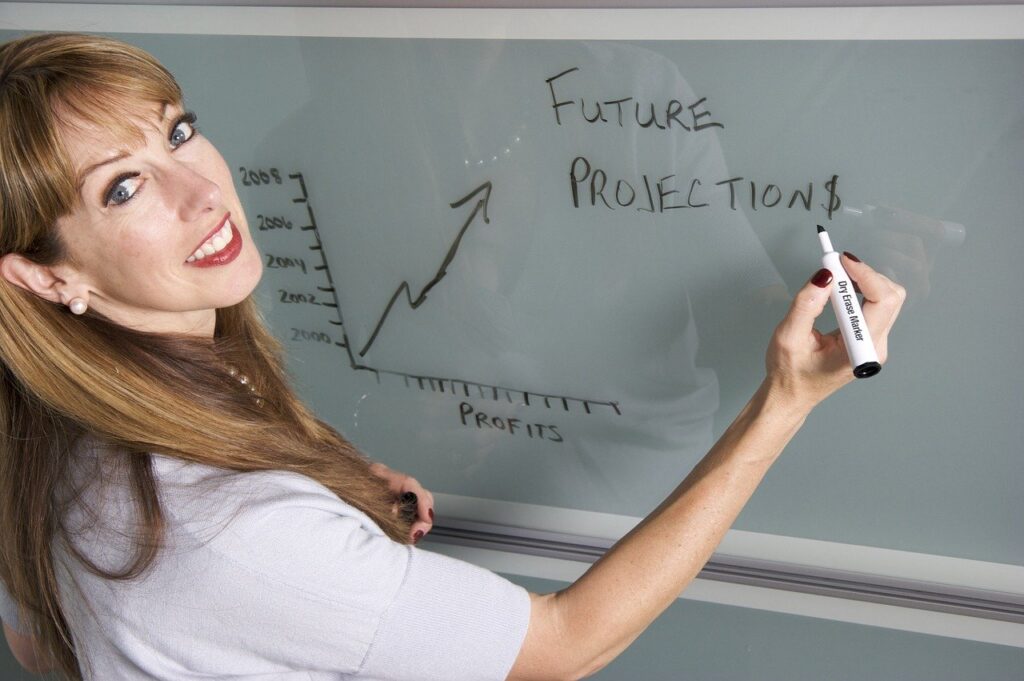
では、丸パクリでうまくいく事例とはどのようなものが多いか。
漫画系では多いと思いませんか?
・漫画のタッチ(見た目)
・ナレーション(セリフ)
・題材(漫画のテーマ)
いろんなチャンネルがありますが、比較的漫画チャンネルは同じようなジャンルで、同じような作り方でも伸びている事実があります。
他にも『ピアノで駅で弾いてみた』みたいな動画も多いですよね。
あれは『上手なピアノ演奏』『ちょっとしたドッキリ』『驚く先を見たい』という部分は共通していて、
企画や内容が同じであればYouTube側も『他にもこんなんあるよ』と関連表示されるケースも多かったです。
企業系や事業者系でもあります。
整体師やヨガ、ダイエットなどは同じようなタイトルも多く、それでも伸びてるチャンネルも多いわけですね。
これは『視聴者層の絶対数』も関係してくるジャンルがありますが、全てうまくいってるわけではないです。
埋もれているだけであって、実際は同じよな編集やタイトルつけても全く伸びないチャンネルも多いです(目に触れてないだけ)
そして丸パクリとまではいかなくとも、同じ良うなコンテンツを発信してうまくいくケースは、
やはり『過去の他チャンネルよりも、もっと詳しい動画』を意識して作られてる方が多いです。
見ているところが『視聴者』なのか、『見た目を真似する』のかで、違いが出てくると思います。
ウェブのSEOも全く同じ考え方なので、YouTubeもGoogle。つまり、YouTubeにとっても『視聴者』を大事にしていることがわかります。
ということは、『動画コンテンツの質が大事』と私は思います。
例外は『検索ボリュームが極端に上がったキーワード』であったり、テレビやニュースで取り上げられた内容であれば伸びることもあります。
でも、そのブームが落ち着いたなら、また元通りになるのもYouTubeなわけです。
まとめ

早い話が、ただ見た目だけ真似しても成果には繋がりにくい。
大事なのは見ているユーザーがどう感じるか、ということは動画のコンテンツの質を高めていく努力も必要ということだと思います。
テクニックはあくまでもテクニック。
本質的に大事にすべきなのは『動画そのもの』ということでした。
ということで、今回の記事は『YouTubeで伸びてるチャンネルを丸パクリしてもうまくいかないケース』という内容でしたが、いかがでしたか?
もし参考になったと感じていただければ嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
